日常に忍び込んでいる芸術は、得てして芸術と見なされぬまま、当たり前の如く存在し続けている。どこかで見たことはあるんだけど、誰が制作しているとかあまり気にしたことがない、気にしようにも日常過ぎて聞くことすらしないとか、まあ、日々色々なことが起こりうるので仕方がないことではあるが、労働として産み落とされた表現として存在している。何度も言うが、当たり前の如く存在する表現には、何かと注意散漫になるものであり、記憶としての残像はあるものの、曖昧なものとして処理されている感がある。なので、なにやら似たテイストの記憶が折り重なって頭の中で整理されてしまうものは残念でならないのだが、そうならぬよう制作する方々は、日々自分なりの哲学を掲げ、表現を繰り返す。あくまで日本での話として個人的意見に過ぎないことを補足として入れておくが、日常に溢れている表現のほとんどが労働として落とし込まれたものであり、対価が支払われている。例えば、イラストレーションといわれるものも、オファーがあり、それに沿って制作する、労働としての仕事であり、経済にのっとったものであると考える。労働の数で評価が問われる部分も多々あるのだが、イラストレーターとして活動する方々の半数以上が生計を考えての葛藤と共に生活を営んでいる。決して否定的な話ではなく、日本でのイラストレーターの存在は様々な時代や環境の変化によって、少し特殊な職業として変化し続けているように思われる。
 |
 |
 |
今回ご紹介する和田誠の作品だが、かなりの皆さんが脳裏に焼き付いているのではないだろうか。毎週「週刊文春」の表紙を描かれているので、毎週新作が見られるという点においては、かなり日常に慣れ親しんだものとして理解されているのだろう。30年以上表紙を描き続けているということに驚きを隠せないのだが、どの作品も、どこかホッとする安心感があるのに、都会的である。私は、単行本の装丁やテレビ(某映画番組)のオープニング等で慣れ親しんだ、というより、ファンであったので、どこか書きづらい部分もあるのだが、和田誠がイラストレーターだと認識しつつも映画の監督をしたり、脚本を書いたり、デザイン(アートディレクション)をしたり、作詞作曲したりと多才な活動をされていたことも知っていたし、その活動もチェックをしていた。なのに、やはりイラストレーターとしての肩書きしか浮かんでこないのだ。


Agent&Creative company 代表取締役兼プロデューサー。新しい才能に目を向け、プロデュースからディレクションを業務とする。ギャラリーとは異なり展示施設を持たず、人に力を注ぐ業務展開を行い、様々な才能を輩出。作家マネジメント及びプロデュースを手掛けながら、付随する業務を全てこなす。その他に、制作部門を独立させ<diffusion.>の代表も兼任。商業施設、広告等のアートディレクション、デザインも受注し、制作物のプロデュース、プランニングまで手掛ける。
http://www.philspace.com/



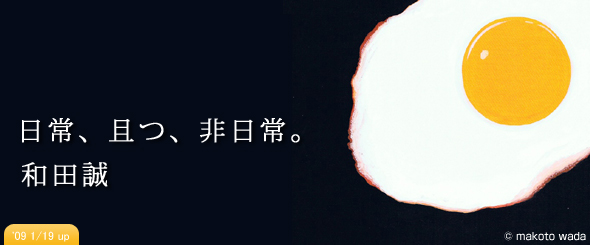
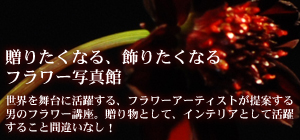
 Vol.22
Vol.22 Vol.21
Vol.21 Vol.20
Vol.20 Vol.19
Vol.19 Vol.18
Vol.18 Vol.17
Vol.17 Vol.16
Vol.16 Vol.15
Vol.15 Vol.14
Vol.14 Vol.13
Vol.13