我が世の春を謳歌してきた時計業界も、世界的不況で戦略を変えざるを得ません。特にアメリカとロシアが壊滅的な状況に陥っており、ここ数年の主流だった(そして彼らの趣向に合わせた)巨大で派手な時計が売れなくなりました。
そこで多くの時計メーカーは、世界中で安定した評価を受ける“シンプルで端正なデザイン”の時計を中心にするべく戦略変更。その結果SIHH会場では、実際に買いたいと思えるモデルが多い一方で、単純に「凄い!」とため息が漏れる突飛なモデルが姿を消してしまいました。
ユーザー目線で考えれば非常にうれしい傾向ですが、ジャーナリスト目線で考えると、華やかさと目新しさに欠けており、ちょっと物足りない…。機械式時計は実用品ではなく趣味のモノになった以上、感動と興奮をもたらすようなモデルがないと、そこにロマンを抱けないのです。
しかしこんな時代だからこそ輝くのが小規模なメーカーたち。彼らは有能なサプライヤーと手を組むことで従業員も工房も最低限で済ませる小回りが利く経営体制なので、もはや大規模メーカーでは実現不可能になりつつある突飛な時計だって少数限定で作ることができます。
しかもそのような時計を買えるような大富豪は世界中に何千人といます。どんなモノでも購入できる彼らにとって、“希少性”だけが所有欲を刺激するキーワード。例え数千万円レベルであっても、年産数十本というレアピースであれば「人と同じ時計は欲しくない」と考える彼らが、先を争うように買い求めるという訳です。
これは時計文化に対する一種のパトロナージュと言えるでしょう。かのアブラアン-ルイ・ブレゲだってフランス王室の庇護の元、いくつもの複雑機構を開発しました。現代は時計好きの実業家がパトロンになって時計文化は支えられているのです。大規模メーカーにはその余裕はなくなりましたが、だからこそユーザー個々の好みに対応してくれ、作り手の顔もしっかり見える小規模メーカーの存在が、より価値を持ってき始めたと言えるでしょう。
今年が初開催となったGTE(Geneva Time Exhibition)には、そんな“小粒でもピリリと辛い”メーカーたちが集まっており、実際に時計を製作した時計師やコンセプター、デザイナーなどが小さなブースで和やかに商談を進めています。
時計クリエイターにとっても、独創的で社会にインパクトを与えることができる“作品”を作れるというのは理想的な環境に違いありません。鶏口牛後という言葉がありますが、自由な気風を失いつつある大手メーカーを飛び出して自身のブランドを立ち上げるという動きは今後も増えるでしょう。
世の中が二局化することに対しては色々な功罪があります。しかし、少なくとも時計好きのビリオネアたちが複雑機構や突飛なデザインに興味を抱き、実際に時計を購入することが、時計文化を発展させる大きな原動力であることは間違いありません。このジャンルにおいて、最も大切なのは誰にも負けない“圧倒的な独創性”。これこそが機械式時計のロマンティシズムを繋いでいくための、大切なキーワードなのです。
 |
個人的に注目したいのは「MCT」。
|
 |
GTEの会場となったのは、国連欧州本部近くのジュネーブ国際カンファレンスセンター。参加ブランド数は38。事前それほど大々的にアナウンスしていなかった割には、5500人もの来場者を集めており、まずは成功と言えるでしょう。今後はインド(ムンバイ)での開催も予定。ターゲットはインドの新興富裕層です。 |
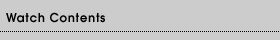
 時計コンシェルジュ Vol.51
時計コンシェルジュ Vol.51時計は世界を救えるか?
 HD3 SLYDE
HD3 SLYDEタッチパネル採用で無限のコンポーネントが生まれる
 時計コンシェルジュ Vol.47
時計コンシェルジュ Vol.47時計メーカー工房取材は、時計の価値を知る良い機会
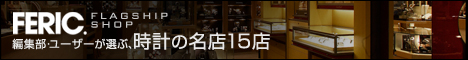

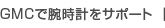


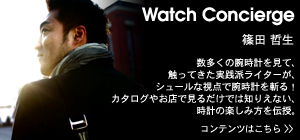
 CP5 EXILE CUP 2012
CP5 EXILE CUP 2012 SHINSAIBASHI NIGHT CRUISE
SHINSAIBASHI NIGHT CRUISE (一社)日本時計輸入協会
(一社)日本時計輸入協会 LONGINES(ロンジン)
LONGINES(ロンジン) 時計コンシェルジュ Vol.50
時計コンシェルジュ Vol.50 時計コンシェルジュ Vol.49
時計コンシェルジュ Vol.49 時計コンシェルジュ Vol.48
時計コンシェルジュ Vol.48