ヨーロッパ出張中に買えなくて困ったもの。それはビール。
仕事終わりに部屋で一杯! のつもりでも、スーパーが18時に閉まってしまう。個人商店であっても、21時以降(ミラノの場合)はアルコール類の販売は禁止で、棚にはカバーが掛けられてしまいます。こんな環境ですから、ちょっと取材時間が伸びた場合は、買い物すらままならないのです。
欧州では残業が少ないと聞きますが、これって残業していると食糧が買えなくなるからみんな早く帰るのかも。その証拠に、時計メーカーの職員は、朝の6時から働いて16時に帰宅しますから…。明るい時間帯からプライベートタイムに入るのは優雅かもしれませんが、そこまで前倒しで生活する必要があるのでしょうか? むしろ時間に縛られているようにも思えます。
なぜヨーロッパ社会はここまで時間に管理されているんでしょう。
その理由が「時計の社会史」(中公新書 角山栄著)という本に書いてありました。
かつて人間は日の出とともに活動し、日暮れとともに眠りに就く生活をしており、その時代に主につかわれていた時計は、主に日時計でした。しかし機械式時計が発明されると、時間は人々を管理するための道具となります。特に顕著だったのが労働時間。産業革命によっていち早く産業化が始まったイギリスでは一日の労働時間がきちんと時計によって管理され、15~16時間も働いていたとか。
きっちりと時間を図ることで労働者を締め付けるというシステムは、プライベートにも及んでおり、特にアルコールの販売時間を制限する法律は、工場労働者が深酒をすることで作業効率が下がることを避けるために定められたもの。ストレス解消までも、時間で縛ったのです。
つまり、現在でもスーパーの閉店時間が早かったり、日曜日に全店舗が閉まったりするのも、このような「時計による管理社会」の名残といえるでしょう。
その点日本の場合は、アルコールだっていつでも買えますし、店舗は年中無休が基本。バスや電車も遅くまで動いており、24時間をどう使うかは自由です。このあいまいで自由な時間感覚に慣れてしまうと、ビールすら自由に買えないほど雁字搦めに時間を管理される社会には、なかなか馴染めません。
 |
夕暮れ迫る18時頃のニューシャテルのメインストリート。まだ空はぼんやり明るいのに、すでに店舗は閉まり、歩く人もまばら。 |  |
裏通りはすでに閑散としており、もうすでに一日が終わっています。 |
 |
「時計の社会史」(中公新書)角山 栄著 “時”をめぐって営まれてきた人類の生活模様を書き記した名著。時計が社会に与えた影響を知ることができる。 |
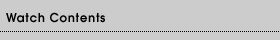
 時計コンシェルジュ Vol.51
時計コンシェルジュ Vol.51時計は世界を救えるか?
 HD3 SLYDE
HD3 SLYDEタッチパネル採用で無限のコンポーネントが生まれる
 時計コンシェルジュ Vol.47
時計コンシェルジュ Vol.47時計メーカー工房取材は、時計の価値を知る良い機会
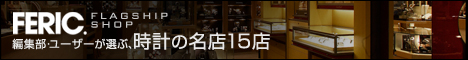

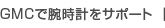
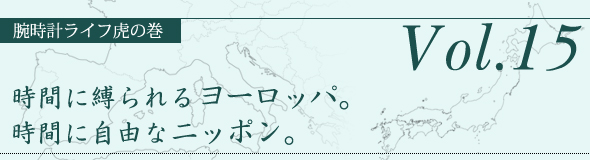

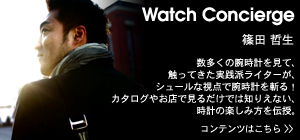
 CP5 EXILE CUP 2012
CP5 EXILE CUP 2012 SHINSAIBASHI NIGHT CRUISE
SHINSAIBASHI NIGHT CRUISE (一社)日本時計輸入協会
(一社)日本時計輸入協会 LONGINES(ロンジン)
LONGINES(ロンジン) 時計コンシェルジュ Vol.50
時計コンシェルジュ Vol.50 時計コンシェルジュ Vol.49
時計コンシェルジュ Vol.49 時計コンシェルジュ Vol.48
時計コンシェルジュ Vol.48