そんな北国の歴史の中にぽっかりと開けたカッパ淵を後にすれば、すぐ近くにある常堅寺の境内から焚き火の微かな煙が立ち上っていました。そういえば焚き火を見るのも、もう随分と久しぶりの気がします。
この「カッパ淵」からほど遠くない場所に、「伝承園」があります。国の重要文化財である「旧菊池家住宅」を始め、敷地内に数棟の古民家を移設し、南部曲り家での豪農の暮らしを再現している場所。
ここにはレストランもあって、遠野の伝統的な料理を味わうことができます。
 |
 |
 |
例えば「ひっつみ」(¥500)。すいとんにも似た素朴な料理ですが、出汁が香り高く美味しい。
そしてもうひとつ、これはすごいですよ。「けいらん」(¥320)。外見が鶏の卵に似ているのでこの名がついたと言いますが、この団子の中に何が入っていると思いますか? こし餡なんです。私は「けいらん」を青森県の東通村と、秋田県の鹿角市で食べたことがありますが、餡入り団子という共通項はあっても、それぞれ少しずつ違う。この遠野の「けいらん」では、団子が沈んでいるのはただのお湯。東通村と鹿角市では、いずれも醤油味の出汁でした。澄し汁の中に甘い団子を入れる。ちょっと不思議な感覚です。所変われば味変わる、ということでしょうか。
ちなみに『遠野物語』とは、柳田國男が後に“日本のグリム”と呼ばれることになる遠野出身の青年、佐々木喜善に話してもらった民話を書きとめたものですが、この「伝承園」にはそんな佐々木喜善の記念館があるほか、予約制で昔話の実演もあります。不思議な物語を語って聞かせる北国独特の抑揚は、まるで子守唄のように音楽的でさえあり、そして聴き慣れぬ語彙は、初めて耳にするはずなのになぜか、聴く者の胸を懐かしさでいっぱいにします。
「昔話とは動物のようなものです」――そんな風に教えてくれた遠野の人がいました。伝説は植物、昔話は動物なのだそうです。曰く、伝説はその舞台の地名がはっきりしている。つまり土地に根を張るものだ。一方、「昔々あるところに……」と始まる昔話は、土地も時代も曖昧だ。それは自由に世界を駆け回るということも意味する……。
そしてもしかしたらその自由さこそが、柳田國男を惹きつけたのかもしれませんね。『遠野物語』の序文にはこう書かれています。
――願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。
そう、“平地人”とは都市に生きる人。当然、柳田自身もそこに含まれたのでしょう。しかし彼が佐々木喜善に聴かされた遠野に息づく昔話は、そうした平地人の常識にまったく縛られることがない。遠野はおそらく、柳田國男にとってのユートピアだったのでしょう。土地にも時代にも縛られない、昔話の故郷。つまりはどこでもあり、そしてどこでもない場所。だから遠野は美しく、そして懐かしいのです。それはあなたの、そして私の故郷でもあり得るのでしょう。そう、昔話がここに静かに生き続ける限りは。
■カッパ淵 |
■伝承園 |
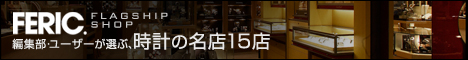

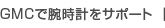


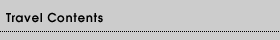
 みちのくの黄金卿・平泉
みちのくの黄金卿・平泉 特集「北陸・トロッコ列車の旅酷暑の夏におすすめ 黒部峡谷鉄道を行く」
特集「北陸・トロッコ列車の旅酷暑の夏におすすめ 黒部峡谷鉄道を行く」 特集「湘南の夏、始まる」
特集「湘南の夏、始まる」 特集「プレミアムホテルの愉しみ セント レジス ホテル 大阪」
特集「プレミアムホテルの愉しみ セント レジス ホテル 大阪」 金融エンターテイメントカフェでコモディティサミットを開催
金融エンターテイメントカフェでコモディティサミットを開催 特集「水の都コペンハーゲンに北欧デザインの源流を見る」
特集「水の都コペンハーゲンに北欧デザインの源流を見る」 特集「沖縄の先にある小国「台湾」で食事・温泉・異文化を楽しむ」
特集「沖縄の先にある小国「台湾」で食事・温泉・異文化を楽しむ」 香港で始まったワイン投資に注目 金や不動産よりも確実!?
香港で始まったワイン投資に注目 金や不動産よりも確実!? 街に芸術があふれている 北欧の大都市 オスロを旅する
街に芸術があふれている 北欧の大都市 オスロを旅する 「洋上の我が家」にようこそ 豪華客船「セブンシーズ・ナビゲーター」 横浜に初寄航する
「洋上の我が家」にようこそ 豪華客船「セブンシーズ・ナビゲーター」 横浜に初寄航する 「世界一美しい航路」 ノルウェー・フィヨルドを巡る船旅
「世界一美しい航路」 ノルウェー・フィヨルドを巡る船旅