カーネーション、その種類は多岐にわたり、これほど絶妙な色が揃うものは無いのではと思うほどです。その数は、1200種類以上で年間200~300種類くらいが入れ替わるというので驚きます。それだけ需要も高いという事ですね。
スペイン、モナコなどの国花でもあるカーネーションは、ヨーロッパでは芸術のモチーフとして用いられたり、香りの強い変種はワインの香りづけに美食家の間で持てはやされたりと、古くから愛されていたことがわかります。
日本へは、徳川時代に伝来し、本格的にハウス栽培がおこなわれ始め、今年は100周年といわれています。

『母の日にカーネーション?』
母の日といえばカーネーション! と今ではこの2つはセットになっていますね。簡単には、カーネーションが母性愛を象徴する花であること(キリストが十字架に架けられた時、聖母マリアの流した涙にカーネーションが咲いたといわれているようです)、母の日提唱者アンナ・ジャービスの母親の好きな花がカーネーションだったこと。このようなエピソードを知ると、見慣れたカーネーションをより深い気持ちで贈れそうです。
私の店でも、毎年カーネーションをお求めに大勢の方が来て下さいます。普段より値段も立派になりますが、気に入ったものを吟味して種類豊富に揃えます。
『レリシア スタイル』
Release=解放するという意味からつけられた“レリシア”。
 |
 |
花が咲き始める前の蕾の段階で、一輪一輪手で丁寧に花びらの周りのガクをはずし、花びらを解放したもの。これにより、本来蕾の中で隠れていた花の変化を直接見ることができ、スタンダードのものより大きな花になります。千葉のカーネーション生産の第一人者の方が開発された世界に誇る技術です。
『私流カーネーション』
カーネーションは比較的持ちも良く、年中あるところも重宝です。私の中では、カーネーションは“表情”というより“色”として見ることが多いところが特徴です。そして、普通見落とされがちな葉にとても魅力を感じます。クルクルとカールしているのです。それも、全てのカーネーションがしているわけではなく、その種類のカーネーションがいつもクルクルとカールしているとは限りません。市場でも、『葉がクルクルしているカーネーションがいいのだけど』といって、『葉がクルクルですか?』と売り場の方に驚かれています。
 |
 |
いかがでしょうか? クルクルした葉、とても愛しく見えませんか? 生け方では艶めいた表情も出してくれます。
花は、自分が魅力的に感じる部分を誇張して生けることです。自身の美の感覚とその花の個性とが遇い交わって、新たな感動が生まれるのだと思います。
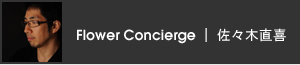
フローリスト こもの花苑
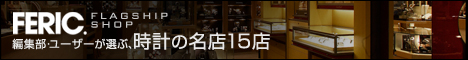

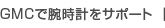

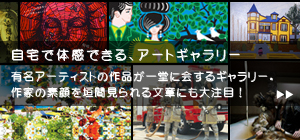
 Vol.07 09 5/1 UP
Vol.07 09 5/1 UP Vol.06 09 4/1 UP
Vol.06 09 4/1 UP Vol.05 09 3/2 UP
Vol.05 09 3/2 UP Vol.04 09 2/2 UP
Vol.04 09 2/2 UP Vol.03 09 1/5 UP
Vol.03 09 1/5 UP Vol.02 08 12/1 UP
Vol.02 08 12/1 UP Vol.01 08 11/5 UP
Vol.01 08 11/5 UP